【代表メッセージ】良い企業風土を作り上げるには【理念経営㊱】
- 西里喜明

- 2025年2月10日
- 読了時間: 3分

ある企業のプロジェクト活動を想像してみてほしい。
◆プロジェクトメンバーA氏:
マネージャーに怒られるのが嫌なので、ミスしたことは気が付かないことにして隠しておこう(後でバレル可能性大)
◆プロジェクトメンバーB氏:
(ミスを犯した真面目なB氏)ミスは自分が頑張って取り返せば何とかなるからマネ
ージャーには黙っておこう
◆マネージャーM氏:
メンバーから悪い報告や相談もないので、PJは順調に進んでいるだろうとマネージャーは何も気にしない日々を送っている
このプロジェクトの今後の展開はどうなるだろうか。各人に自分なりの理屈があり、納得したい想いや気持ちがあるだろう。しかし、組織としてはどうだろうか?
自律した組織ならメンバー各自で解決して事なきを得る可能性もあるが、その場合でも仕事の成果を高め、リスクやトラブルを防ぐには情報の共有が必要である。
人間学を学ぶ月刊誌『致知(2025年3月号)』に特集に次の言葉が掲載されている。
「功の成るのは、成る日に成るに非ず、けだし必ず由って起きるところにある」
(中国宋代の人「蘇老泉<そろうせん>」の『管仲論』にある言葉だという)
人が成功するのは、ある日突然、成功するわけではない。すべて平素の努力の集積によって成功するということである。
この後に言葉はこう続く。
「禍の作(おこ)るは作るに作らず、また必ず由って兆(きざ)すところにあり」
禍(わざわい)が起こるのも、ある日急に起こるのではなく、前から必ずその兆しがあるという言う事である。禍は未然に消し、功を成すべく、不断の努力をする、それが長の条件だということをこの言葉は教えている。
中国の紀元前の言葉であるが、現代でも十分に吟味に値する言葉といえよう。
「ローマは一日にして成らず」という言葉もあるが、ローマ帝国建設ほどの大事業ではなくても我々の小さな組織や会社における事業への取り組みも一朝一夕で達成できるものではない。
「蘇老泉」の言葉を今一度考えてみよう。
成功は平素の努力の集積の賜物であり、禍はある日突然起こるものではなく、必ずその前に何らかの兆しが起こるものである。
良い企業風土を作り上げるには、平素の真摯な努力の集積が必要であり、禍の芽は小さい(早い)うちに取り除いて正常の姿に戻す努力が必要だということである。
企業の不祥事も急に起るのではなく、必ず前に何らかの兆しが起こっていることを念頭に常日頃から、経営理念を軸とした判断と行動に注力する必要があるのではないか。
良い企業風土は自浄能力を持ち、悪い組織風土は隠ぺい体質を持つ。
人間として、経営者として良い企業風土醸成のため内省と成長のサイクルを築き上げていきたいものである。
株式会社CSDコンサルタンツ
代表取締役 西里 喜明


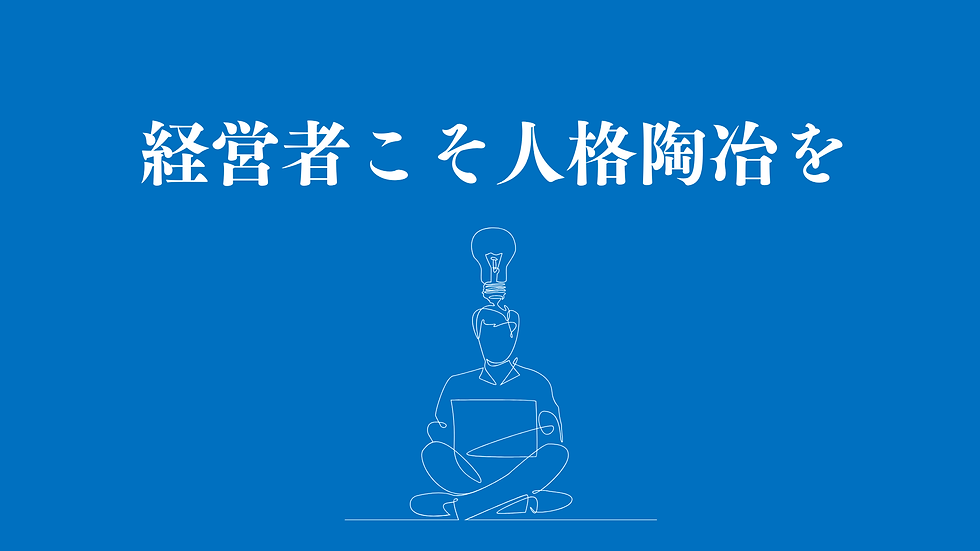
コメント